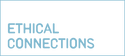「ゴミ」を「チャリティー」として寄付する!?
服をゴミ箱に捨てるのは気分が悪いですよね。
幸いなことに、「寄付」という気持ちの良い代替案があります。
突然、古着を捨てることが美しい寄付の行為になるのです。

しかし、それが私たち自身に「良い行い」だと言い聞かせているだけの話だとしたら?
私が着た服は困っている誰かの役に立っているのだ!という慰めの言葉が、実は過剰消費の連鎖を助長しているとしたらどうでしょう?
「良い行い」のために後で全部手放すことができるのなら、いくら買ってもいいのでしょうか。
現実的に、着古した汚れた服を欲しがる人はいるのでしょうか。
特に、裕福な欧米や日本で、誰かがTシャツを手放すのを待っている人は本当にいるのでしょうか?
私たちは、服を寄付することは寛大な行為だと信じたいものです。
チャリティーショップや衣料品用回収箱に寄付することは、クローゼットを軽くするだけでなく、私たちの良心を清らかに保つことでもあります。
しかし、その寄付が贈り物ではなく、重荷になっている可能性はないでしょうか。
問題を解決しているのではなく、問題を輸出しているだけだとしたら?
毎週、何百万着もの古着が北半球からガーナ、ケニア、ナイジェリア、フィリピン、ハイチといった国々に運ばれています。
ほとんどの人は、これらの衣服がありがたく受け取られ、再利用されることを想像するでしょう。
しかし実際は、最大40%が使用不可能なもの、つまり汚れていたり、破損していたり、価値のないものなのです。
到着した衣類は、埋め立て地に捨てられたり、燃やされたり、あるいはすでにゴミの管理に苦労している地域の水路や浜辺を詰まらせてしまう原因になるのです。
これは慈善事業ではありません。廃棄物処理のアウトソーシングなのだ。
援助という幻想
「寛容」という言葉に包まれたこのシステムは、援助しているように見せかけながら、深い弊害を生み出しています。
ガーナのなどの国々がゴミ捨て場として扱われ、北半球における過剰生産と過剰消費の結果を請け負うことを余儀なくされています。
送られるものの多くは、もともと長命ではなかった低品質のファストファッションなのです。
私たちはそれを 「寄付 」と呼んでいます。
しかし実際には、私たちの責任を他の誰か、つまりNOと言う力を持たない人々に転嫁しているだけなのです。

H&M - リサイクルか、チャリティか、それとも単なるマーケティングか?
日本で最も有名な衣料品「寄付」プログラムのひとつに、H&Mが行っているものがあります。
ほとんどの店舗に足を踏み入れると、サスティナビリティをアピールする看板が掲げられた回収ボックスが目に入ることでしょう。
うれしいことに、どのブランドの服であっても1袋につき500円のクーポン券がもらえます。
何だか得した気分ですよね。ですが、しっかりと精査してみましょう。
H&Mの衣料品回収プログラムは、消費を減らすために存在するのではなく、消費を促すためのものです。
古着を持って来ることで割引を受け、すぐに新しい服を買い足すことを奨励するのです。
これは、環境への配慮を装った、マーケティングとしての巧妙なリサイクルシステムです。
多くの消費者は、これらの服は困っている人たちの手に渡ると思っています。
ですが、実際には古着は選別され、再利用や再利用されるのはごく一部です。
大部分は海外の中古市場に輸出され、そこから多くは埋立地に捨てられたり、燃やされたり、ガーナの海岸や水路のような場所に捨てられたりするのです。
衣服の再利用というアイデアは価値があります。
しかし、これを慈善活動と呼んだり、気候変動対策と混同するのはやめましょう。
これは小売業のマーケティング戦略なのです。
私たち消費者へ気分よく廃棄物を処理する方法を提示することで、消費を好調に維持するための完璧な例と言えるでしょう。

地域経済を圧迫する
一見すると、古着の売買は経済的なチャンスを生み出しているように見えるかもしれません。
確かに、それも一理あります。
輸入業者、転売業者、廃棄物処理業者......多くの人々が、生きるためにこの仕事に頼っています。
しかし、その実情は搾取的で不安定な環境で、低賃金で、保護もほとんどありません。
さらに、中古輸入品が溢れかえることで地域経済に壊滅的な打撃を与えています。
かつては多くの国で、仕立て屋やデザイナー、伝統的な織物メーカーが盛況でしたが、今では、寄付された安価な衣服の山に押され、ことごとく値下げされているのです。
その結果、本物の地元産業が滅びてしまいます。
地元ブランドは成長できず、文化的なファッションの伝統は侵食されてしまうのです。
地域社会は依存のサイクルに閉じ込められ、サスティナビリティや主権を構築する余地がなくなってしまいます。
果たしてこれが慈善事業なのでしょうか。
これは笑顔の仮面を被った経済的窒息です。

偽装された新植民地主義
ここで「新植民地主義」という言葉が登場しますが、兵士や国旗の問題ではありません。
「新植民地主義」とは不平等なシステムのことです。
貧しい国々が裕福な国々に経済的に縛られているために、発展することを妨げられているのです。
南半球に位置する途上国は廃棄物を受け取り、仕事を失い、貧困の責任を負わされる一方、日本を含む北側諸国は責任を回避し、それを慈善事業と呼び、いい事をした気持ちになっています。
要するに、私たちは混乱を引き起こし、その後始末をさせるために他国にゴミを送るのです。
グローバルな富の格差
不均衡は環境問題や経済問題だけではありません。
それはグローバルで全体的な問題なのです。
毎年、約5兆ドルが南半球から北半球に流れ、援助、投資、融資を通じて戻ってくるのはわずか2兆ドルです。
私たちは、南半球はしばしば北半球からの援助によって「発展」していると聞かされています。
しかし、数字が示すのはその逆です。
南半球は原材料や安価な労働力を供給し、いまや廃棄物の管理さえも行うことで北半球を発展させているのです。

今こそ「慈善」ではなく「正義」の時
では、私たちはどうすればいいのでしょうか。
大きな問題ではありますが、はじめの一歩は正直になることです。
まずは廃棄物をを寄付のように装うのをやめる必要があります。
公正、正義、そしてサスティナビリティを重視するならば、そうしなければなりません。
- 輸出される衣料品には厳格な品質管理を実施すること。着用不可能なものは送るべきではない。
- 本当は廃棄処分なのに「チャリティー」と呼ぶ事をやめること。
- 受け手の声に耳を傾けること。私たちが何を処分したいのかではなく、彼らが何を必要としているのかを聞くこと。
- 南半球の地場産業を支援する事。その地域に拠点を置くブランド、デザイナー、組合から購入する。
- 過剰生産を縮小する。すべての根源は、必要以上のものを作っていることだ。
これは罪悪感の問題ではなく、意識の問題です。
もし私たちが本当に公正さを信じるのであれば、私たちの服が使い終わった後にどこへ行くのかを考える必要があります。
単に寄付箱に入れるだけでなく、海を渡り、埋立地に捨てられ、何世紀も前から続く不平等なシステムに組み込まれていることに思いを馳せることが大切です。
南半球の方々は私たちの廃棄物を必要としていません。
彼らに必要なのは、正義であり、尊敬であり、自らのやり方で繁栄する自由なのです。
Follow us on Instagram
インスタグラムで最新情報や舞台裏、ブログリリースのお知らせを配信しています!